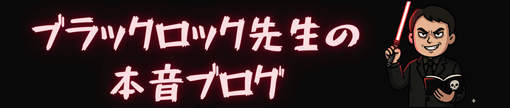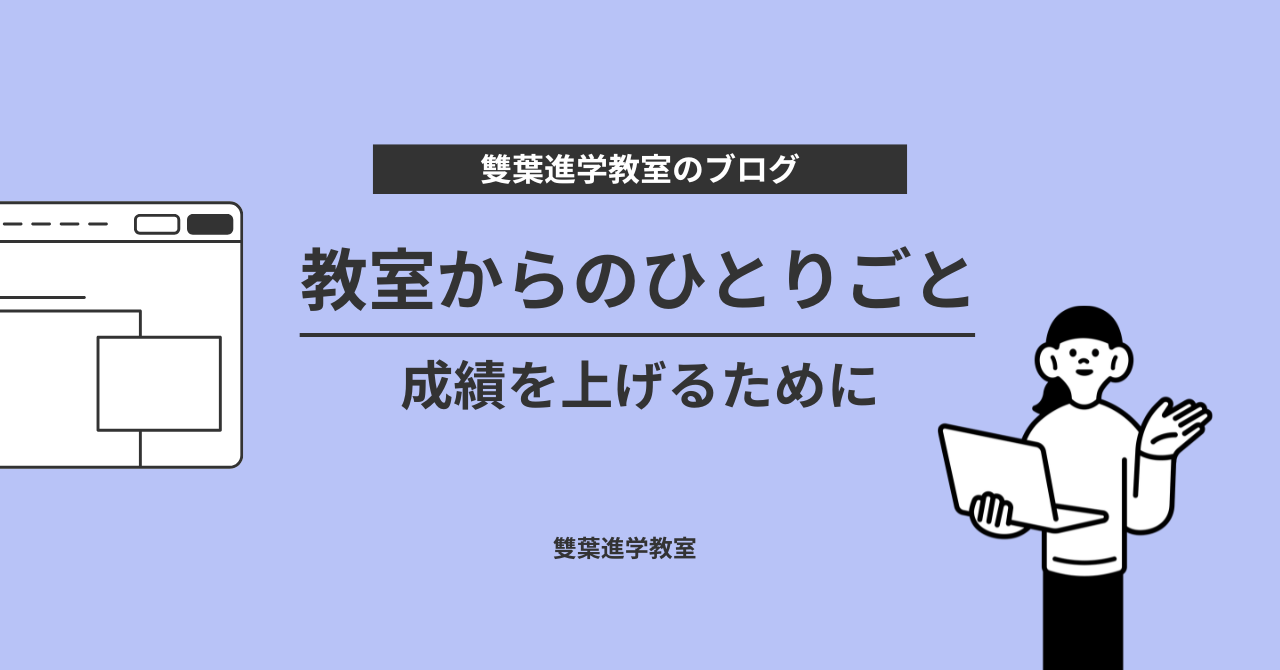~計算力・文章題・論理力のすべてはここにつながる~
■「答えだけ」では見えないもの
塾で指導していて感じることのひとつに、途中の式を書かない子が意外と多い、ということがあります。
ノートを見ても、表やグラフには何の書き込みもなく、答えだけがポツン……。
簡単な問題なら合っていることもありますが、標準的な問題になると、ほとんどが間違っています。
しかも「符号を間違えただけ」「ちょっとした計算ミス」と軽く受け止めてしまうことが多いのです。
しかし、それは実はとても重大なサインです。
なぜなら、「途中の式を書かない=考える過程がない」ということだからです。
■途中の式がないと、文章題が解けない
経験上、途中の式を書かない生徒の多くは、文章題が苦手です。
そして実は、「文章題が苦手」という以前に、計算の段階で止まってしまっていることも少なくありません。
つまり、「解けない」以前に「解こうとしていない」状態です。
数学の文章題は、問題文を読み取り、情報を整理し、自分の言葉で式に直す力が必要です。
この「整理」や「式にする」過程がまさに“途中の式”そのもの。
そこを省略してしまえば、論理のつながりが見えず、考えが飛んでしまうのです。
■「高校になってから数学が苦手になった」本当の理由
「高校に入ってから数学が急に難しくなった」と言う生徒は多いですが、
実際には“急に難しくなった”のではありません。
もともと途中の式を書かずに「なんとなく解いていた」部分が、通用しなくなっただけなのです。
高校数学では、途中の式を書かずに正解できる問題など、ほとんどありません。
小さな省略の積み重ねが、後になって大きな壁になる——
これは長年の指導で何度も見てきた現実です。
■どうすればいいのか
答えはシンプルです。
どんなに簡単な問題でも、「途中の式を書く」ことを習慣にする。
たとえ暗算でできるような計算でも、あえて書くことに意味があります。
また、できれば「何を求めたいのか」を一言添えて書くとさらに良いです。
これは単なる計算練習ではなく、論理を積み上げていく練習です。
途中の式は、筋道を立てて考える“地図”のようなもの。
それが書けるようになると、文章題も、応用問題も、ぐっと見通しがよくなります。
■最後に
数学ができるようになるとは、正しい答えを出せることではなく、
正しい考え方で答えにたどり着ける力を身につけることです。
途中の式は、その「考える力」を育てる最良のトレーニングです。
もしお子さんが「途中の式なんて面倒」と言っていたら、
「それが将来の数学力を支える土台になるんだよ」と、ぜひ伝えてあげてください。